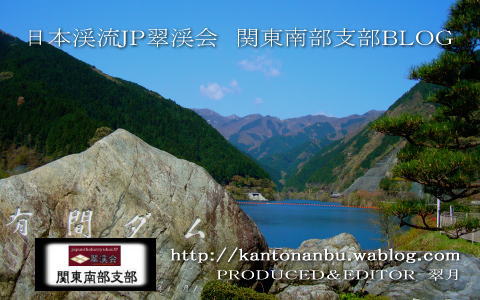続・小金沢連嶺の渓流【再回想】2

続・小金沢連嶺の渓流【再回想】2
そもそも大菩薩嶺より南の小金沢連嶺は、笹子峠まで続いたほぼ南北に連なる山々だ。五百円札の富士山もこの連嶺の、雁ガ腹摺り山から撮影されたものなのは有名だ。小金沢山はその連嶺の主峰ではあるが、大菩薩連嶺の一部だ。つまり小金沢(葛野川)の頭だ。日本百名山に選定された、大菩薩連嶺本嶺の大菩薩嶺へは、交通機関が、裂石を中心とした登頂の為、葛野川水系及び、丹波山村、小菅村からの登道は限られている、謂わば裏山の感はある。小金沢は出合いから滝や淵が連続している。水量が多い時は要注意だ。単独で入る事が多かったので、無理は出来なかった。鶏淵や林道淵は釜も大きく、手竿では探りきれないポイントだ。今は林道が大峠を越え、真木川のハマイバに抜けているが、まだその頃は、大菩薩沢出合いの次に入る、マミエ谷あたり迄で、さらに延長工事の為、掘削中だった。だから源流より、下流から、大菩薩沢出合いの間が本命だった。ある年、林道から大菩薩沢へ降りていて周囲を釣っていた。釣り人が右岸から滝を巻いて降りて来た。聞くとよく来ると言う山梨弁の釣り人だ。昨年事故があり、知り合いが怪我をしたということだ。こんな若い子供みたいな釣り人がよく一人でくるな?って感じで、警告してくれた。『渓が深いから、奥には入れない、止めた方がよい』…と。小金沢は危険だが釣り人も多い。やはり型のよいヤマメやイワナが釣れるからだろう。いつも1日一回は釣り人に会う谷だった。だから比較的人がいない、土室川に釣りを場変更する事が多かった。
翠月
コメントを投稿する