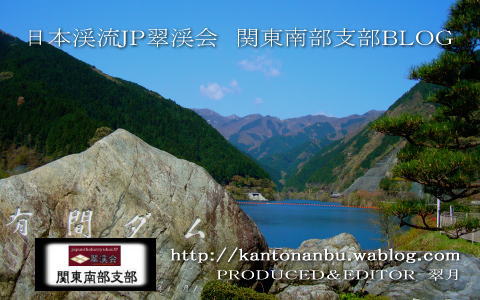翠渓会関東圏本部・関東南部支部支部釣行【第二十一陣】1

翠渓会関東圏本部・関東南部支部支部釣行【第二十一陣】1
『春の上信越国境・四万川水系』
残された渓、忘れられた渓 移しイワナの子孫たち
■マタギ
マタギは、東北地方・北海道で古い方法を用いて集団で狩猟を行う者の集団。一般にはクマ獲り猟師として知られるが獲物はクマだけではない(後述)。古くは山立(やまだち)といった。特に青森県と秋田県のマタギが有名である。その歴史は平安時代にまで遡るが、近代的な装備の狩猟者(ハンター)とは異なることに注意する必要がある。森林の減少やカモシカの禁猟化により、本来的なマタギ猟を行う者は減少している。マタギの語源は諸説あって不明である。最も有力なものは、アイヌ語で「冬の人」・狩猟を意味するマタンギ・マタンギトノがなまったものだという説である。ただし、日本語のマタギという語が先にあり、この語がアイヌ語に取り入れられたという説もある。マタギは夏季は農業などを営み、冬になると集団をつくって白神山地のような奥深い森林で数日間に渡って狩猟を行う。狩猟の対象は主にカモシカとクマだが、カモシカの狩猟が禁じられたため、現在では春先に冬眠から覚めたクマを狩猟するマタギが多い。夏、狩りの季節の前に、あらかじめ森林の中にマタギ小屋と呼ばれる簡易な小屋を立て、ここに米などを運び込んでおく。狩猟が始まると、ここで寝泊りして狩りを行う。この小屋は非常に簡易なものなので、長持ちはしない。壊れると、翌年はまた新しい小屋がつくられる。1つの集団の人数は通常8〜10名程度だが、狩猟の対象によっては数十人編成となることもある。マタギの頭をシカリと呼ぶ。集団の各人はそれぞれ仕事を分担する。通常は、クマを谷から尾根に追いたて、先回りしている鉄砲打ち(ブッパ)が仕留める狩猟(巻き狩り)を行う。現代では鉄砲が使用されるが、槍や毒矢を用いた時代もあった。マタギの使用する武器は時代と共に進歩し、明治時代には村田銃、その後はスコープ付きのライフル等どんどん高性能な武器を利用している。しかし、高性能な武器の存在が、集団で狩りを行う必然性をなくし、マタギ文化が衰退した一因ともなっている。マタギは、山の中ではマタギ言葉という特別な言葉を使い、口笛を吹くこと、鉄砲をまたぐなど禁忌事項も多くあった。厳しい雪山の自然に立ち向かってきたマタギには、「山は山の神が支配する場所、そして熊は山の神からの授かり物」「猟に入る前には水垢離(みずごり)を行う」など独特の信仰を持ち、獲物をしとめたときなどには特別の呪文を唱えるという。マタギの信仰する山の神は醜女であるとされ、より醜いオコゼを供えることで神が喜ぶとされる。マタギ発祥の地と云われる阿仁では戦前まで、一人前のマタギとして集団に属する儀式(成人式)の際、新成人ははと(ペニス)をいきり立たせて、山の神との象徴的な交合を行って結婚をする儀式が執り行われていた。これはマタギ衆以外に公言することが禁忌とされはばかられていたが、戦後の民俗調査での聞き取り記録で明らかになった。これらの風習について、アイヌ文化の影響を指摘する声がある。また、マタギ言葉もアイヌ語との類似性を指摘されている。これらのアイヌ文化とマタギ文化の類似性は、紀行家の菅江真澄によって江戸時代から指摘されていた。
翠渓会渓流事典&NAVI
■関東南部渓流事典
……suikeikai…………………………………………………
■日本渓流会JP翠渓会・会長代理
■関東圏基幹G本部統括本部長・関東管領
■関東南部支部・初代支部長
■翠渓会本部会評定衆
■日本渓流会本部代表執権取締役【翠月:suigetsu】
■翠渓会HP: http://www.suikeikai.jp
■翠渓会MAIL: suikeikai@coda.ocn.ne.jp
■翠渓会渓流事典&NAVI
…………………………………………………suikeikai……