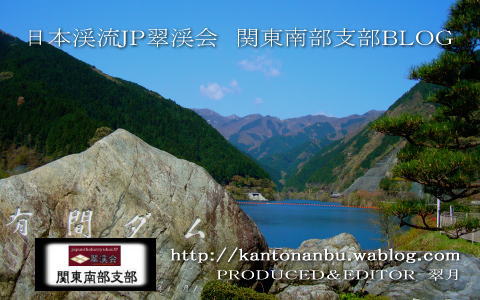翠渓会関東圏本部・関東南部支部支部釣行【第二十四陣】1
『奥多摩の渓流・コスゲヤマメを求めて・・・』
多摩川源流の里・過去に移植された放流の子孫が残る沢
■小菅川・雄滝(大滝)
落差10m程の二条滝、今倉沢の白糸の滝、棚倉沢の棚倉滝、鯨沢の鯨滝など
小菅川には幾つかの美しい滝がある。新緑、紅葉の時期は特に素晴らしい。
白糸の滝は滝手前50mに20台ほどの駐車場(トイレ有)、雄滝は下り口100m手前に10台程の駐車場(トイレ有)がある
小菅の谷は本来ヤマメのみの谷で、支流の棚倉沢には移植の岩魚がいたが例外で本流も殆どヤマメだったが近年はニッコウイワナが放流され増えている。
一部の沢には現存のヤマメが僅かに生息している。
翠渓会渓流事典&NAVI
■関東南部渓流事典
……suikeikai…………………………………………………
■日本渓流会JP翠渓会・会長代理
■関東圏基幹G本部統括本部長・関東管領
■関東南部支部・初代支部長
■翠渓会本部会評定衆
■日本渓流会本部代表執権取締役【翠月:suigetsu】
■翠渓会HP: http://www.suikeikai.jp
■翠渓会MAIL: suikeikai@coda.ocn.ne.jp
■翠渓会渓流事典&NAVI
…………………………………………………suikeikai……Read More
翠渓会関東圏本部・関東南部支部支部釣行【第二十三陣】3
『上信越高原の渓流・吾妻川水系源流』
吾妻川源流、高原野菜の里 嬬恋村
■新鹿沢温泉・鹿鳴館
鹿沢温泉・新鹿沢温泉は静かな高原にある。鹿沢温泉(かざわおんせん)は、群馬県吾妻郡嬬恋村(旧国上野国)にある温泉。温泉は鹿沢温泉と、新鹿沢温泉の2つに分かれ、両者は距離も離れている。この2つは区別される場合と一緒に扱われる場合がある。両者とも上信越高原国立公園の区域内に位置する。鹿沢温泉は標高1500mの高所にあり、日本秘湯を守る会にも属する一軒宿の紅葉館が存在する。新鹿沢温泉は標高1300mの高所にあり、鹿沢温泉からの引湯であり、旅館やホテルが多数ある。また周辺には鹿沢スノーエリアなどのスキー場も多い。
■鹿沢温泉観光協会
翠渓会渓流事典&NAVI
■関東南部渓流事典
……suikeikai…………………………………………………
■日本渓流会JP翠渓会・会長代理
■関東圏基幹G本部統括本部長・関東管領
■関東南部支部・初代支部長
■翠渓会本部会評定衆
■日本渓流会本部代表執権取締役【翠月:suigetsu】
■翠渓会HP: http://www.suikeikai.jp
■翠渓会MAIL: suikeikai@coda.ocn.ne.jp
■翠渓会渓流事典&NAVI
…………………………………………………suikeikai……Read More
翠渓会関東圏本部・関東南部支部支部釣行【第二十三陣】2
『上信越高原の渓流・吾妻川水系源流』
吾妻川源流、高原野菜の里 嬬恋村
■吾妻川源流・湯ノ尻川
湯ノ尻川は吾妻川源流の一つで本流は鳥居峠からの鳥居川だが、環境は湯ノ尻川の方が良い。白樺もある高原地形を流れる穏やかな渓流・・・
とても気分良く釣れる渓流だ。新鹿沢温泉鹿鳴館の反対側の車道の先にから渓沿いに湯ノ尻川遊歩道があり「山女橋」・「岩魚橋」も健在。
翠渓会渓流事典&NAVI
■関東南部渓流事典
……suikeikai…………………………………………………
■日本渓流会JP翠渓会・会長代理
■関東圏基幹G本部統括本部長・関東管領
■関東南部支部・初代支部長
■翠渓会本部会評定衆
■日本渓流会本部代表執権取締役【翠月:suigetsu】
■翠渓会HP: http://www.suikeikai.jp
■翠渓会MAIL: suikeikai@coda.ocn.ne.jp
■翠渓会渓流事典&NAVI
…………………………………………………suikeikai……Read More
翠渓会関東圏本部・関東南部支部支部釣行【第二十三陣】1
『上信越高原の渓流・吾妻川水系源流』
吾妻川源流、高原野菜の里 嬬恋村
■鹿沢高原休暇村
高原リゾートを満喫できる施設。
■吾妻川
吾妻川(あがつまがわ)は、群馬県を流れる一級河川。利根川の支流である。
草津温泉や万座温泉などを起源とする強酸性の水が流れ込み水質はきわめて強い酸性である。周囲の鉱山からの硫黄も含まれ、魚はほとんど生息しない死の川であった。支流には普通の水が流れるものが多く、そこではサクラマスなどが生息する。雪解け水で酸性度が低くなったときに入り込んだものと言われる。昭和中期に草津町に中和工場が建設され、川に石灰を注入することで水質が安定した。現在は下流部でアユ漁なども行うことができる川となっている。1952年に八ッ場ダムの建設が持ち上がり、水没予定地の長野原町の地元住民が激しく反発し賛成派と反対派で町を二分する大問題となる。1992年にダム建設推進を前提とする基本協定書が長野原町、群馬県、建設省の間で結ばれ、1994年にはダム関連工事が始まった。近年の水余りの傾向などもあって建設に異を唱える人々も少なくないが、利水単価が最近のダムとしては安いことや、吾妻川流域での豪雨に対応した治水施設の要となる施設であることから、国や関係都県の行政側では事業推進の姿勢を長らく崩さなかった。2009年の民主党政権の誕生に伴い、公共事業見直しのシンボル的扱いとして中止が宣言され、先行きが不透明となるに至った。
翠渓会渓流事典&NAVI
■関東南部渓流事典
……suikeikai…………………………………………………
■日本渓流会JP翠渓会・会長代理
■関東圏基幹G本部統括本部長・関東管領
■関東南部支部・初代支部長
■翠渓会本部会評定衆
■日本渓流会本部代表執権取締役【翠月:suigetsu】
■翠渓会HP: http://www.suikeikai.jp
■翠渓会MAIL: suikeikai@coda.ocn.ne.jp
■翠渓会渓流事典&NAVI
…………………………………………………suikeikai……Read More
翠渓会関東圏本部・関東南部支部支部釣行【第二十二陣】3
『上信越国境 吾妻渓谷に残された渓』
八ツ場ダムの存亡と川原湯温泉
■川原湯温泉 共同浴場 王湯
【料金】大人300円
【入浴料+休憩室】大人600円
【営業時間】10:00〜18:00
川原湯温泉(かわらゆおんせん)は、群馬県吾妻郡長野原町(旧・上野国)にある温泉。吾妻川の谷間の上部の道路沿いに、数軒の旅館がひしめく様に存在する。共同浴場は「王湯」「笹湯」、混浴の「聖天様露天風呂」が存在する。温泉街は八ッ場ダム建設に伴い、いずれ移転する予定である。
■川原湯温泉観光協会公式HP
翠渓会渓流事典&NAVI
■関東南部渓流事典
……suikeikai…………………………………………………
■日本渓流会JP翠渓会・会長代理
■関東圏基幹G本部統括本部長・関東管領
■関東南部支部・初代支部長
■翠渓会本部会評定衆
■日本渓流会本部代表執権取締役【翠月:suigetsu】
■翠渓会HP: http://www.suikeikai.jp
■翠渓会MAIL: suikeikai@coda.ocn.ne.jp
■翠渓会渓流事典&NAVI
…………………………………………………suikeikai……Read More
翠渓会関東圏本部・関東南部支部支部釣行【第二十二陣】2
『上信越国境 吾妻渓谷に残された渓』
八ツ場ダムの存亡と川原湯温泉
川原湯温泉付近までの吾妻渓谷の吾妻川本流には魚類は生息していないが、右岸左岸からの支流が釣り場になっている。主な支流にはイワナまたはヤマメが生息している。本流との交流が無いが支流に細々と暮らしているイワナヤマメたちだ。下流から雁ヶ沢、鍛冶屋敷川、八ツ場ダム近くの八ツ場沢、滝沢、温井沢、大沢、久森沢、不動沢、深沢、小倉沢等である。
翠渓会渓流事典&NAVI
■関東南部渓流事典
……suikeikai…………………………………………………
■日本渓流会JP翠渓会・会長代理
■関東圏基幹G本部統括本部長・関東管領
■関東南部支部・初代支部長
■翠渓会本部会評定衆
■日本渓流会本部代表執権取締役【翠月:suigetsu】
■翠渓会HP: http://www.suikeikai.jp
■翠渓会MAIL: suikeikai@coda.ocn.ne.jp
■翠渓会渓流事典&NAVI
…………………………………………………suikeikai……Read More
翠渓会関東圏本部・関東南部支部支部釣行【第二十二陣】1
『上信越国境 吾妻渓谷に残された渓』
八ツ場ダムの存亡と川原湯温泉
■八ッ場ダムの問題と川原湯温泉
温泉街の有る場所は八ッ場ダムで完成する湖によって沈む場所に存在し、貴重な自然湧出の源泉もダム湖に沈む予定である。対策として温泉街最上部の予定湖面より高い地点にボーリング調査によって新源泉が掘り当てられ、そこに新温泉街を造成中である。しかし、湯量・泉質ともに旧源泉とは異なり、今後観光地として成り立のかを不安視する意見もある。ただし、マニフェストで八ッ場ダムの建設中止を主張する民主党に政権交代したことにより、今後の動向は不透明になっており、一部の住民らはダム建設中止反対の署名運動を行なっている。新源泉は高温の源泉のため、源泉にて温泉卵を作る光景がよく見られる。また、新源泉の近くでは足湯が楽しめるようになっている。
翠渓会渓流事典&NAVI
■関東南部渓流事典
……suikeikai…………………………………………………
■日本渓流会JP翠渓会・会長代理
■関東圏基幹G本部統括本部長・関東管領
■関東南部支部・初代支部長
■翠渓会本部会評定衆
■日本渓流会本部代表執権取締役【翠月:suigetsu】
■翠渓会HP: http://www.suikeikai.jp
■翠渓会MAIL: suikeikai@coda.ocn.ne.jp
■翠渓会渓流事典&NAVI
…………………………………………………suikeikai……Read More
翠渓会関東圏本部・関東南部支部支部釣行【第二十一陣】3
『春の上信越国境・四万川水系』
残された渓、忘れられた渓 移しイワナの子孫たち
■「隠し沢」にある移しイワナの楽園郷
昔の旅マタギ流れの職漁師たちは草津温泉や四万温泉の宿に注文の魚を卸していた。羽州や越後から来た旅マタギ流れではない元々地元に代々住んでいた木地師や猟師も職漁師を兼ねている場合もある。彼らも昔は落人だったり他の地域から移住して住み着いた人々の子孫である事も少なくない。職漁師たちは当然安定した釣果を求められる訳で、ただ職漁の釣りをしていたのではない。マタギたちの『移しイワナ』を応用し自分たち独自の「隠し沢」に漁場を持っていた。型は食べやすいサイズでまずは一定の数を揃えるのが職漁師だ。その様な魚を増やせる隠し沢は増水で流されてしまうような廊下を持つ厳しい沢でなく、どちらかというと平凡な沢で、開けた渓が多い。また下流が滝でもその上に放たれた岩魚もいる。開けた渓で最も釣果の挙がる釣り方・・・彼らは餌も使うが効率の良い【毛鉤釣り=テンカラ】での釣法だったのだろう。平凡な沢や開けた沢の方が毛鉤釣りには好都合だ。
そういった移しイワナの子孫を求めるならまずは読図とマタギたちの足取りを追うことになる。ヒントはマタギたちが使う地形語と山師たちの痕跡にある。地図に無い職漁の「隠し沢」への道・・・昔の人は正確な地図もないのにどうやって地形を読んでいたのか・・・? 不思議であるがマタギたちは独自の文化(言葉や地形語等)を持っていて東北〜越後〜上信越方面、遠くは越中までその子孫たちの痕跡がある。山の民の広大なネットワークは一般庶民には到底分からない独自のルートも持っていた。その隠し沢には未だにイワナの子孫たちが息づいていた。
■秋田マタギの里『阿仁マタギ』
翠渓会渓流事典&NAVI
■関東南部渓流事典
……suikeikai…………………………………………………
■日本渓流会JP翠渓会・会長代理
■関東圏基幹G本部統括本部長・関東管領
■関東南部支部・初代支部長
■翠渓会本部会評定衆
■日本渓流会本部代表執権取締役【翠月:suigetsu】
■翠渓会HP: http://www.suikeikai.jp
■翠渓会MAIL: suikeikai@coda.ocn.ne.jp
■翠渓会渓流事典&NAVI
…………………………………………………suikeikai……Read More
翠渓会関東圏本部・関東南部支部支部釣行【第二十一陣】2
『春の上信越国境・四万川水系』
残された渓、忘れられた渓 移しイワナの子孫たち
■隠し沢のイワナ(移しイワナ)
七〜八寸位までの魚が多い。(写真は九寸)
職漁の商品として対象になるイワナのサイズは六寸〜七寸と比較的小型。
マタギ=猟人と言えば「熊撃ち」、いい獲物が獲れるという情報は彼らの広大なネットワークから入ってきた。相手は山の民で、木地師や鉱山師、鍛冶師もいただろう、活動範囲は東北〜越後(会津)〜越中〜美濃の主に日本海側を中心にした猟域で縦横にルートを持っていた。イワナ釣りは熊撃ちの食糧目的だったが、後の山漁=職漁になっていく。旅マタギたちにとっては山漁=職漁が熊撃ち以外の「生活の糧」になっていた。信越秋山郷は特に秋田旅マタギの伝承が良く残っている。鈴木牧之の秋山紀行に詳しく載っている。<秋田の旅マタギ〜狩猟と山漁の暮らし>鈴木牧之は切明(当時は湯本)で秋田から来た若き旅マタギ=秋田の狩人二人と対面している。熊の皮を身に纏いいかにも勇猛そうな・・と記している。
■書籍 鈴木牧之「秋山記行」
鈴木牧之「秋山記行」
現代語訳
訳・解説 磯部定吉
恒文社
税込価格: ¥1,890 (本体 : ¥1,800)
サイズ : 20cm / 117p 図版16p
■書籍 鈴木牧之「秋山記行」復製版
野島出版刊 鈴木牧之「秋山記行」
■鈴木牧之の秋山紀行
■旅マタギの記録・・・秋山紀行
翠渓会渓流事典&NAVI
■関東南部渓流事典
……suikeikai…………………………………………………
■日本渓流会JP翠渓会・会長代理
■関東圏基幹G本部統括本部長・関東管領
■関東南部支部・初代支部長
■翠渓会本部会評定衆
■日本渓流会本部代表執権取締役【翠月:suigetsu】
■翠渓会HP: http://www.suikeikai.jp
■翠渓会MAIL: suikeikai@coda.ocn.ne.jp
■翠渓会渓流事典&NAVI
…………………………………………………suikeikai……Read More
翠渓会関東圏本部・関東南部支部支部釣行【第二十一陣】1
『春の上信越国境・四万川水系』
残された渓、忘れられた渓 移しイワナの子孫たち
■マタギ
マタギは、東北地方・北海道で古い方法を用いて集団で狩猟を行う者の集団。一般にはクマ獲り猟師として知られるが獲物はクマだけではない(後述)。古くは山立(やまだち)といった。特に青森県と秋田県のマタギが有名である。その歴史は平安時代にまで遡るが、近代的な装備の狩猟者(ハンター)とは異なることに注意する必要がある。森林の減少やカモシカの禁猟化により、本来的なマタギ猟を行う者は減少している。マタギの語源は諸説あって不明である。最も有力なものは、アイヌ語で「冬の人」・狩猟を意味するマタンギ・マタンギトノがなまったものだという説である。ただし、日本語のマタギという語が先にあり、この語がアイヌ語に取り入れられたという説もある。マタギは夏季は農業などを営み、冬になると集団をつくって白神山地のような奥深い森林で数日間に渡って狩猟を行う。狩猟の対象は主にカモシカとクマだが、カモシカの狩猟が禁じられたため、現在では春先に冬眠から覚めたクマを狩猟するマタギが多い。夏、狩りの季節の前に、あらかじめ森林の中にマタギ小屋と呼ばれる簡易な小屋を立て、ここに米などを運び込んでおく。狩猟が始まると、ここで寝泊りして狩りを行う。この小屋は非常に簡易なものなので、長持ちはしない。壊れると、翌年はまた新しい小屋がつくられる。1つの集団の人数は通常8〜10名程度だが、狩猟の対象によっては数十人編成となることもある。マタギの頭をシカリと呼ぶ。集団の各人はそれぞれ仕事を分担する。通常は、クマを谷から尾根に追いたて、先回りしている鉄砲打ち(ブッパ)が仕留める狩猟(巻き狩り)を行う。現代では鉄砲が使用されるが、槍や毒矢を用いた時代もあった。マタギの使用する武器は時代と共に進歩し、明治時代には村田銃、その後はスコープ付きのライフル等どんどん高性能な武器を利用している。しかし、高性能な武器の存在が、集団で狩りを行う必然性をなくし、マタギ文化が衰退した一因ともなっている。マタギは、山の中ではマタギ言葉という特別な言葉を使い、口笛を吹くこと、鉄砲をまたぐなど禁忌事項も多くあった。厳しい雪山の自然に立ち向かってきたマタギには、「山は山の神が支配する場所、そして熊は山の神からの授かり物」「猟に入る前には水垢離(みずごり)を行う」など独特の信仰を持ち、獲物をしとめたときなどには特別の呪文を唱えるという。マタギの信仰する山の神は醜女であるとされ、より醜いオコゼを供えることで神が喜ぶとされる。マタギ発祥の地と云われる阿仁では戦前まで、一人前のマタギとして集団に属する儀式(成人式)の際、新成人ははと(ペニス)をいきり立たせて、山の神との象徴的な交合を行って結婚をする儀式が執り行われていた。これはマタギ衆以外に公言することが禁忌とされはばかられていたが、戦後の民俗調査での聞き取り記録で明らかになった。これらの風習について、アイヌ文化の影響を指摘する声がある。また、マタギ言葉もアイヌ語との類似性を指摘されている。これらのアイヌ文化とマタギ文化の類似性は、紀行家の菅江真澄によって江戸時代から指摘されていた。
翠渓会渓流事典&NAVI
■関東南部渓流事典
……suikeikai…………………………………………………
■日本渓流会JP翠渓会・会長代理
■関東圏基幹G本部統括本部長・関東管領
■関東南部支部・初代支部長
■翠渓会本部会評定衆
■日本渓流会本部代表執権取締役【翠月:suigetsu】
■翠渓会HP: http://www.suikeikai.jp
■翠渓会MAIL: suikeikai@coda.ocn.ne.jp
■翠渓会渓流事典&NAVI
…………………………………………………suikeikai……Read More